小児歯科について

親御さんと歯科医院で協力して
お子さんの健康を守りましょう
小児歯科はむし歯の治療と、むし歯の予防が治療の中心です。個々のお子さんの成長に合わせて治療を選び、むし歯ゼロを目標に健康で良好な口腔機能を整えていくことで、健全な子どもたちを育んでいきます。歯科医院での治療だけでなく、ご家庭での口腔ケアの説明などによって親御さんをサポートしながら、歯科医院との二人三脚で取り組んでいきます。
- 歯を痛がっている
- 永久歯が生えてこない
- 歯科医院に行きたがらない
- 悪癖を治してほしい
- 歯みがき指導を受けたい
- 歯科検診を受けたい
- フッ素を塗布したい
子どもの歯を守る
6つのポイント
01
子どもの
お口の状態に
関心を持ちましょう
02
食事は顎全体で
よく噛むように!
姿勢にも気を
つかいましょう
03
歯みがきを
しましょう!
まずは
習慣化から!
04
おやつ・食事は
計画的に!
05
成長に合った
食事を摂りましょう
06
歯の外傷に
気を付けましょう
当院の小児歯科

「噛み神フーフー」という考えを
大切にしています
当院の小児歯科では、離乳食期の食事内容に着目した「噛み神フーフー」を推奨しています。一般的に子どもへの口移しはNGと言われていますが、細菌学的に問題ないと当院では考えています。しっかり噛むことで将来的に歯並びを整えるとともに、睡眠時無呼吸の防止、腸内細菌良好化などの効果が期待できます。
お子さんの食生活も意識しましょう
最近では、ご飯ではなくパン食が増加していることにより、むし歯や歯周病の罹患率が増えていると報告されています。特に菓子パンなどの超加工食品と呼ばれるものの影響は大きいため、できるだけ雑穀米、発酵食品などの和食の食事を心がけるようにしましょう。また、食事を摂る時間やタイミングも意識しながら正しい食生活をおくることで、お口の健康を守っていきましょう。

お子さんの
ペースに合わせた治療方針
子どもにとって、歯科医院での治療は怖いというイメージが多かれ少なかれあります。当院では、嫌がるお子さんに対して無理やり治療はしません。お子さんの緊張が解けるよう柔らかい雰囲気を心がけており、治療内容や器具を丁寧に説明して、納得いただいてから治療を行います。お子さんのペースに合わせて治療を進めさせていただきます。
治療内容
フッ素塗布

シーラント
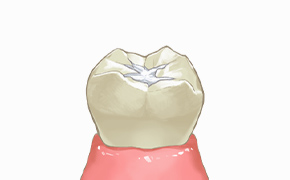
ブラッシング指導



